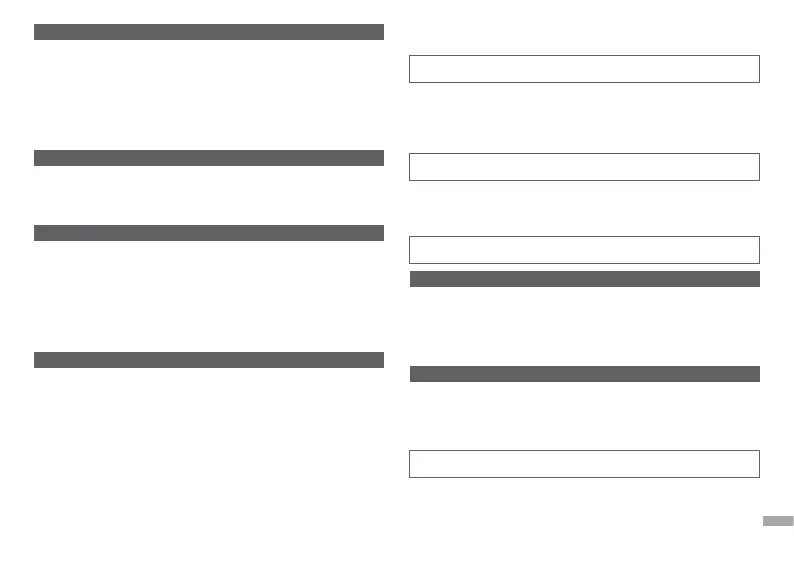JA
121
製品パーツ
(a) 取扱い説明書保管
コン パートメント
(b) バックレ スト
(c) リクライニ ング ヘッドレスト
(d) ヘッドレスト高さ調節装置
(e) ブースター
(f) ラップ ベルトガイド
(g) 肩ベルトガイド
(h) 線形側面衝撃保護(L.S.P.)
(i) ISOFIX ロッキングアーム
(j) ISOFIX調節ハンドル
(k) ISOFIXリリースボタン
(l) ISOFIX安全インジケーター
(m) ISOFIXアンカーポイント
最初の組立
バックレ スト (b)をブースター軸の取っ手で留めて、ブースター(e)に接続させる。
それからバックレ スト (b)を前方に曲げる。線形側面衝撃保護(L.S.P.)(h)は 、カ ー シ
ートをパッケージから出すと自動的に広がり ます。 車のドアに面した線形側面衝
撃保護(L.S.P.)が、完全に広がっていることを、運 転開始前に確認してください。
車内での正しい位置
ISOFIXロッキングアーム(i)を引っ込めると、カーシートを自動三点式ベルトを備え
る車に使用することができます。ISOFIXを使用する場合は、www.cybex-online.
comで互換車両の一覧をご確認ください。
身長135 ㎝を超えるお子様の場合は、Solution T i-Fix とお客様の車両との互換性
が減少する場合があります。互換車両の一覧を参照して、チャイルドシートをすべ
てのヘッドレスト位置で制限なく使用できるかどうか確認してください。
例外的に、チャイルドシートを助手席で使用できる場合もあります。 自動車メーカ
ーの推奨事項に常に従ってください。
チャイルドシートの車への取付け
1. 以下に気を付けてください。
• 車内の背もたれが、直立位置にロックされていること。
• 助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、ベルト経路に影響を与えるこ
となく、座 席をできる限り後ろに下げること。
2. ブースター(e) 下のISOFIX 調節ハンドル (j) を使用して、2つのISOFIXロッキン
グアームを (i) 最大長さまで引っ張る。
3. ISOFIXロッキングアーム(i) を180°ひねってISOFIXアンカーポイント(m)の方向
に向ける。
4. チャイルドシートを車内の適切な座席上に置く。
5. 2つのISOFIXロッキングアーム(i)をISOFIXアンカーポイント(m)の所定の位置
に「カチッ」という音がして収まるまで押す。
6. ISOFIX調節ハンドル (j)を使用して、カーシートを車の座席に向かって押す。
7. チャイルドシートのバックレスト (b)の表面全体を、車両座席の背もたれが支
えていることを確認する。
💡
車のヘッドレストが邪魔な場合には、一番高い位置まで引っ張るか、完全に取
り除く(車の座席が後ろ向きの場合を除く)。
8. カーシートが固定されたことを確かめるため、ISOFIXアンカーポイント(m)か
ら引出そうとしてみてください。 シート両側の緑色の安全インジケーター(l)が
はっきりと見える必 要 があります。
9. シートをISOFIXなしに使用する場合には、シート底部に保管することができま
す。
💡
ISOFIXを使用すると、車への接続ができ、それによりお子さんの安全性が増し
ます。 お子さんは、それでも車の3点式ベルトで固定する必要があります。
10. 車両ドア反対側の線形側面衝撃ガード(L.S.P.)(h)を閉じるには、後方にスライ
ドさせてから、定位置にロックされるまで内側に押します。線形側面衝撃ガー
ド(L.S.P.)(h)をもう一度広げるには、L.S.P.の「PRESS」(押す)と書かれている部
分 を 強く押してくだ さい 。
💡
車内に十分なスペースがない場合には、L.S.P.を使用することなくカーシート を
使用することもできます。
チャイルドシートの車からの取外し
取付け手順を逆に行ってください。
1. ISOFIXリリースボタン(k)を押して、ISOFIXロッキングアーム(i) 両側のロックを
解除し、同時にそれらを後ろに引く。
2. ISOFIXアンカーポイント (m)からシートを引っ張り出 す。
3. チャイルドシートを取外し、ISOFIXを取り付けたときと逆の手順で保管する。
リクライ ニング・ヘッドレ スト
リクライ ニング・ヘッドレスト (c)は、お子さんが寝ている間、危険なほど前傾する
ことを防ぐ役に立ちます。 位置は、3つのどれかに設定することができます。 お望
みの位置まで、リクライニング・ヘッドレスト(c)を前に押してください。 元の位置
に戻すには、リクライニング・ヘッドレスト(c)を持ち上げて後ろに引っ張る必要
があります。
💡
お子さんの頭は、常にリクライニング・ヘッドレストに接触している必要があ
ります。
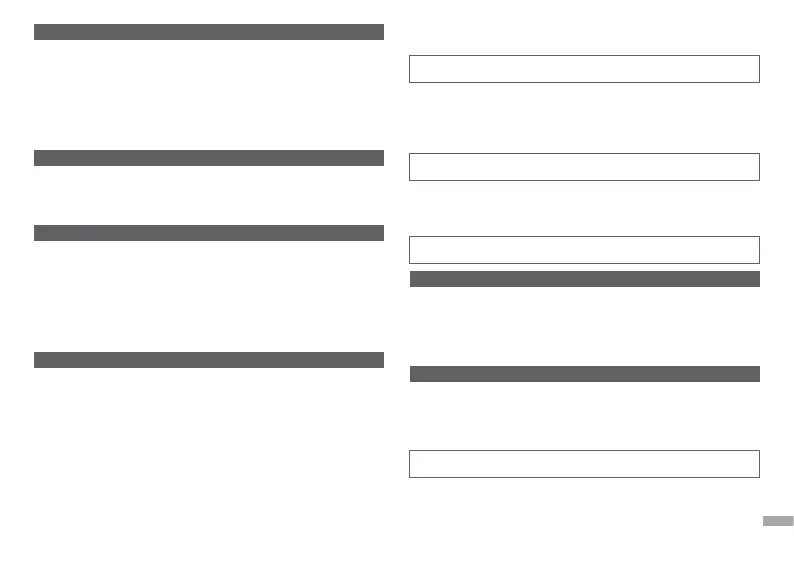 Loading...
Loading...